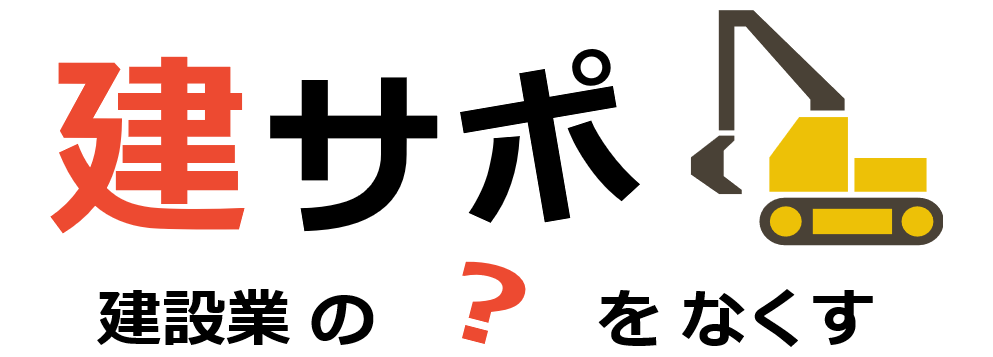建設業許可の申請区分のひとつに「般・特新規」という区分があります。この区分は非常にややこしい区分で専門家でも扱いを間違うことがあるほどです。本記事ではこの「般・特新規」について、該当事例をあげながらわかりやすく解説していきます。
本記事のポイント
般・特新規は許可の申請区分の1つ
未保有の許可区分(一般・特定)の申請で該当
許可番号は既に保有のものが引き継がれる
般・特新規とは?
建設業許可を申請する際、その申請の目的や申請業者の許可保有状況などに応じて、該当する「申請区分」というものを選択しなければなりません。般・特新規とはその申請区分のひとつで、一般建設業の許可もしくは特定建設業の許可のみを持っている業者が、持っていないもう一方の許可区分を申請する際に該当する申請区分です。この定義だけだと少しわかりにくいと思いますので、もう少し具体例も交えて詳しく見ていきましょう。
ちなみに他にも申請区分は以下の5つがあります。詳しく知りたい方は「許可の申請区分5つをわかりやすく徹底解説!」を参照ください。
| 申請区分 | 該当要件 |
| 新規 | 現在許可を受けていない者が許可を申請する場合 例)許可なし⇒管工事業 |
| 許可換え新規 詳しい解説を見る | 現在許可を受けている行政庁以外の行政庁に対し新たに許可を申請する場合 例)管工事業(知事許可)⇒管工事業(大臣許可) |
| 般・特新規 | 一般建設業許可のみを受けている者が新たに特定建設業許可を申請する場合、又はその逆 例)管工事業(一般)⇒管工事業(特定) |
| 業種追加 詳しい解説を見る | 現在保有する許可区分(一般・特定)と同じ許可区分で保有していない業種を追加申請する場合 例)管工事業(一般)⇒管工事業(一般)+塗装工事業(一般) |
| 更新 詳しい解説を見る | 既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請(更新)する場合 例)管工事業(一般)⇒管工事業(一般) |
般・特新規の判定方法
般・特新規は申請区分の中でも区分わけが少しややこしく、特に業種追加などと間違いやすい申請区分です。般・特新規と正しく判定するための手順をご紹介していきます。
①建設業許可を既に持っている
まずこれが大前提になります。許可がなければ般・特新規にはならず必ず「新規」の申請区分です。これは過去に許可を持っていても現在失効していれば同様に「新規」扱いになります。
②保有の許可が一般建設業または特定建設業のみ
この「のみ」という点が極めて重要です。一般も特定もどちらも持っている場合は般・特新規ではなく「業種追加」になるケースが多いです。必ずどちらかの許可区分しか持っていないことが必須です。
③持っていない許可区分の業種を新たに申請する
上記①②を満たしたうえで、その申請者が現在持っていない許可区分(一般・特定)の業種を追加する場合、「般・特新規」に該当すると判定可能です。①~③を満たす具体例としては以下のようなケースがあげられます。
・管工事業(一般)の保有業者⇒管工事業(特定)を申請
・塗装工事業(特定)の保有業者⇒左官工事業(一般)を追加
般・特新規に該当しないケース【要注意】
それでは、一見すると般・特新規に思えますが実はそうではない、注意が必要な般・特新規に該当しない具体例を見ていきましょう。まずは下記のようなケースです。
管工事業(特定)と電気工事業(一般)の保有業者⇒電気工事業(特定)を申請
この場合は、電気工事業が一般から特定に変わるので「般・特新規」のように見えますが、この場合管工事業の方で特定をすでに持っているため、般・特新規ではなく業種追加になります。電気工事業を持っているのに「業種追加」というのは少し違和感を感じるかもしれませんが、一般と特定をすでに持っている業者は般・特新規に該当することはありませんので注意が必要です。
また、次のケースは非常に間違いやすい事例になります
管工事業(特定)と電気工事業(特定)の保有業者⇒管工事業(一般)と電気工事業(一般)を申請
このケースは判定方法で紹介した①~③に該当していますが、この例だけ特例で般・特新規に該当せず通常の「新規」に該当します。なぜかというと、一般から特定への移行は許可の上書きに違い扱いがされますが、特定から一般への移行は一度特定の許可を廃業してから一般を取り直すという扱いになるためです。
そのため、上記の例のような「特定の許可のみを受けている業者が、その特定の許可全部について一般の許可を申請する」場合は、持っている許可がいったんすべて廃業扱いとなるため、一時的になんの許可も持っていない状態になります。そのため、申請する一般の許可は「般・特新規」ではなく「新規」ということになるのです。違いを例であげると下記のようなイメージです。
⇒塗装工事業を一旦廃業扱いとしますが管工事は残る為「般・特新規」
⇒管工事業も塗装工事業も一旦全て廃業する為「新規」
般・特新規の申請実務上の特徴
「新規」と「般・特新」の申請上の実務は基本的にほとんど同じだと考えてください。は般・特新規はあくまでもは新規申請の1種ですので、ある業種について一般から特定に変えるだけだとしても、新しく特定の許可を取るのと同じレベルの審査を受ける必要があります(手数料も新規と同じで一般の場合は9万円、大臣の場合は15万円かかります)。
ただし般・特新規の場合はすでに持っている許可番号が変わらないという点があります。許可番号が変わると不都合が生じるケースもありますのでその点は安心して申請が可能です。
許可申請でお悩みの方は
建設業許可の申請でお悩みの方は、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を代行してもらう方法があります。行政書士に依頼することで下記のようなメリットもあります。
行政書士に代行してもらうメリット
・申請を丸投げできるので業務に専念できる
・建設業法や許認可についての相談窓口ができる
・許可取得にかかる期間が短縮できる
当サイトを運営する建設業許可申請に専門特化した「イロドリ行政書士事務所」も申請代行サービスに対応しておりますので、許可申請を依頼したいという方はぜひ一度以下からご相談頂ければと思います(相談は無料です)。
般・特新規まとめ
以上、ここまで般・特新規についてご紹介してきました。
般・特新規は申請区分の中でも特にややこしく、中でも業種追加と間違えるケースが非常に多いです。判定に迷った場合は申請先の自治体か専門の行政書士などに相談されることをお勧めします。