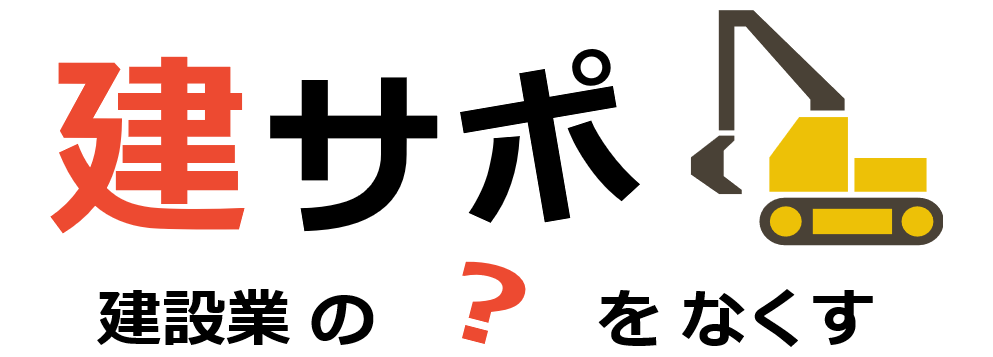「建設業許可を絶対に取りたい…!」そんな事業者様の為に、本記事では建設業許可を取る為に絶対にクリアしなければならない必須の条件6つについてわかりやすくご紹介します。
※2020年10月から施工される改正建設業法に則り記載した最新情報です
本記事のポイント
許可を取るには6つの条件が満たす必要あり
許可取得後に条件が欠けると取消となる
一般建設業と特定建設業で条件が異なる
建設業許可って絶対に必要なの?
そもそも建設業許可がどんな時に必要になるかを最初に確認しておきましょう。
建設業許可は500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上または面積が150平方メートル以上の木造住宅工事の工事)を請け負う場合に必ず必要になる許可のことです。これらの工事を請け負いたい場合は、都道府県知事または国土交通大臣に申請し許可を受けてからでないと工事を請け負ってはいけません(無許可でこれらの工事を請け負うと建設業法違反で懲役刑または罰金刑の対象となります)。
ですので、500万円未満の工事しか請け負わない業者であれば建設業許可を持たずに工事を請け負って問題ありません。また以下のような作業は建設工事に該当しないため許可は不要です。
②建設資材や仮設材等の賃貸
③保守点検のみの委託契約
④工作物の設計業務
⑤地質調査、測量調査
⑥警備業務(交通誘導員)
⑦資材等の売買 契約
こんな場合も建設業許可が必要!
建設業法上は500万円以上の工事を請け負う際に必要と定められていますが、他にも以下のような場合に建設業許可が必要になります。
①公共工事に参加する
②外国人技能実習生を受け入れる
③発注者や元請からの要請
公共工事に参加したり、外国人技能実習生を受け入れる場合、各制度のルールで建設業許可の所有が義務づけられています。また昨今コンプライアンスが重視されるようになり、発注者や元請から許可がないと契約をしないといわれるケースも増えています。これらのケースでは例え請け負う工事が500万円未満であっても建設業許可を取る必要がありますので知っておきましょう。
建設業許可を取るための条件は?
ではこの建設業許可は誰でも取ることができるのでしょうか?実は建設業許可を取るには、以下にあげる6つの条件を満たしている必要があります。この6つの条件を満たさなければ許可は絶対に取ることはできませんし、反対に満たしてさえいれば許可は申請すれば必ず取ることができます。
建設業許可の取得条件(★は難易度)
①経営業務の管理能力(★★★)
②専任技術者 (★★★)
③誠実性 (★☆☆)
④財産的基礎等 (★☆☆)
⑤欠格要件 (★★☆)
⑥社会保険 (★☆☆)
建設業許可の条件① 経営業務の管理能力
まず最初に最もハードルが高い「経営業務の管理能力」を紹介します。建設業許可を取るには、法人であれば役員のうち1名以上が、個人事業であればその個人事業主か支配人が、以下のいずれかの経験を過去にしている必要があります。
①建設業者での法人役員、または個人事業主としての経験が5年以上ある
②建設業者での法人役員や個人事業主に準ずる地位として経営に関わった経験が5年以上ある
③建設業者での法人役員や個人事業主に準ずる地位として業務を補佐した経験が6年以上
①~③のどれか1つでも満たしていればOKですが、②と③は「準ずる地位」の証明は難しく、実際は①で条件クリアを目指すケースがほとんどです。この①をクリアするには、個人事業主や会社の社長(大きい会社の営業所長や支店長でも可)を5年以上している必要があり、多くの申請者にとって最大難易度の条件となっています。なお、この経験が5年ではなく2年でも取れる仕組みが最近設けられましたが、こちらも極めてレアケースかつ証明が難しいのが現状です。
経営業務の管理能力について詳しく知りたい方はコチラ
※レアケースも含めかなり詳しく解説しています
建設業許可の条件② 専任技術者
先ほどの経営業務の管理能力と同じくらいに難しい条件がこれからご紹介する「専任技術者」の条件です。建設業者許可を取るには、各営業所に常勤で働く従業員のうち1人以上が以下の条件を満たしている必要があります。
①取りたい業種に関連する国家資格を持っている
②取りたい業種での実務経験が10年以上ある
※どちらかを満たしていればOK!
この条件を満たした人物のことを「専任技術者」といいます。この専任技術者を条件に置く事で、その会社が一定の技術スキルを持つ事を担保する狙いがあります。この条件は「各営業所に1人以上」なので、営業所が2つ以上あれば、専任技術者も2人以上必要になります。
専任技術者の条件に関する補足
専任技術者として認められる国家資格は国土交通省が定める資格のみが認められます。これらは1級土木施工管理技士や建築士などの難関資格が多く、ここに該当する資格が無い場合は、②の実務経験10年で条件を満たさなければなりません。ここで注意が必要なのが、この実務経験を証明する作業は非常に難しく、例えば自治体によっては10年分の工事の請負契約書を提出するよう求められたりします。国家資格ではなく実務経験で許可を取る場合は申請の難易度が高くなると認識しておきましょう。
なお、この実務経験10年は、業種に関連する学科を卒業していれば、以下の通り必要な年数が短縮されます。
関連する大学の学科を卒業 ▶ 実務経験3年以上でOK
関連する高校の学科を卒業 ▶ 実務経験5年以上でOK
関連する学科については業種ごとに国土交通省が定めている学科である必要があります。これらの関連学科や先ほど述べた国家資格については以下の記事で詳しく紹介していますので参考にしてください。
専任技術者なる為の条件を徹底解説!専任技術者について詳しく知りたい方はコチラ
建設業許可の条件③ 誠実性
建設業許可を取るには、その業者が誠実である事が求められます。以下の条件をクリアしているものは誠実性があるとされ許可の条件をクリアできます。
誠実性クリアの条件
直近5年間で、建築士法や宅地建物取引業法に違反し、許可や免許を取り消されていない事
この条件が求められるのは、個人事業であればその個人事業主と支配人、法人であれば役員や営業所長など経営において重要な役割をもつ人達です。
建設業許可の条件④ 財産的基礎等
建設業許可を取る為には、一定以上の資金力をもっている必要があります。建設工事を着手するには、資材の購入や労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の資金が必要になり、工期も長期化する事から、発注者保護の観点でこのような条件がかされています。
財産的基礎等のクリア条件
①資本金が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力があること
どちらかを満たせばOKです。②の場合は500万円が銀行口座に入っていればそれだけでよく、許可を取る為に知人から借りてきたお金でも問題なく許可がおります。
建設業許可の条件⑤ 欠格要件
建設業許可を取るには、社内に欠格要件に該当する人物がいない事が求められます。欠格要件は、申請する書類と人に関する事項が合わせて15個あり、そのいずれにも該当しない事が必要です。
この欠格要件は社内の従業員全員が対象にはならず、個人事業の場合は個人事業主と支配人、法人の場合は役員や営業所長など経営に関わる人達です。欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当無しと虚偽の申請をすると、そこから5年間は許可を取る事が出来なくなりますので、絶対にしないようにしましょう。
| 番号 | 欠格要件(ひとつでも該当したらダメ) | |
| 書類 | ① | 許可申請書や添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき |
| ② | 許可申請書や添付書類中の重要な事実について記載が欠けているとき | |
| 人 | ① | 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
| ② | 不正の手段で許可を受けた、又は営業停止処分に違反したことで許可を取り消され、取消しになった日から5年を経過しない者 | |
| ③ | ②の取消し処分にかかる通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者 | |
| ④ | ②の取消し処分にかかる通知があった日以前60日以内に、③の廃業の届出をした法人の役員等若しくは令3条使用人(営業所長等)、又は届出をした個人の令3条使用人で、当該届出の日から5年を経過しない者 | |
| ⑤ | 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 | |
| ⑥ | 営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者 | |
| ⑦ | 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ※禁固以上とは「死刑」「懲役」「禁固」が該当します。 | |
| ⑧ | 一定の法律に違反したことで罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | |
| ⑨ | 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 | |
| ⑩ | 申請者が未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者 | |
| ⑪ | 法人でその役員等、又は令3条使用人が上記に該当する者 | |
| ⑫ | 個人でその支配人又は令3条使用人が上記に該当する者 | |
| ⑬ | 暴力団員等にその事業活動を支配されている者 | |
建設業許可の条件⑥ 社会保険加入
この条件は2020年10月から新しく条件として追加されました。社会保険の適用事業所に該当する業者は、社会保険に加入していなければ許可を取ることはできません。対象となるのは社会保険は健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つです。
適用事業者に該当しない場合は加入不要
個人事業主で従業員がいない場合など、社会保険の非適用事業所(加入義務がない事業所)であれば、当然加入していなくても許可を取ることができます。
ウチは加入義務あり?なし?社会保険加入条件について詳しく知りたい方はコチラ
建設業許可の条件一覧
それではここまで紹介した条件を改めてまとめます。建設業許可の条件を確認する上で大切なポイントは「求められる条件」と「その条件が求められる人」の関係性を正しく理解することです。
| 項目 | 求められる条件 | 求められる人 |
| ①経営業務の管理能力 | 法人役員および個人事業主の経験5年以上 | 法人:常勤の役員のうち1人以上 個人:個人事業主もしくは支配人 |
| ②専任技術者 | 業種に関連する国家資格 業種の実務経験10年以上 | 営業所に常勤の従業員 |
| ③誠実性 | 直近5年での法律違反による免許等の取消がない事 | 法人:常勤の役員、営業所長等 個人:個人事業主もしくは支配人 |
| ④財産的基礎等 | 資金力(500万円以上) | 会社として |
| ⑤欠格要件 | 欠格要件への非該当 | 法人:常勤の役員、営業所長等 個人:個人事業主もしくは支配人 |
| ⑥社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入 | 会社として(対象従業員全員) |
条件を満たしてない場合はどうすれば良いですか?
建設業許可を取りたいけど残念ながら条件を満たしていないというケースは非常に多くあります。「それでも許可がどうしても必要なんです!」というご相談も一方で非常に多く受けます。条件を満たしていない場合の対処方法としては以下のようなものが考えられます。
対処法①条件を満たしている人を雇用する
許可条件を満たしていないケースのほとんどは「経営能力(役員経験5年以上)」か「専任技術者(国家資格または実務経験)」をクリアできないケースです。その場合はこれらの条件を満たした人を雇用するしかありません。経営能力をクリアしたい場合は、会社の外部から役員経験や個人事業主の経験がある方を、個人事業の場合は支配人として、法人の場合は役員として会社に入ってもらう事で、条件を満たす事が可能になります。これは専任技術者も同じで、資格保有者や実務経験が10年ある方を雇用すればOKです。
ただしこの場合は常勤役員や正社員になってもらう必要がありますのでいわゆる「名義貸し」のような形での雇用は認めらませんので注意しましょう。
対処法②欠格要件該当者は役員から外す
もし会社役員の誰かが「欠格要件」に該当していて条件がクリアできない場合はその人を役員等のポジションから外す方法があります。誠実性や欠格要件は個人事業主や役員に求められる条件ですので、もし役員に該当者がいれば、その人物を役員から外し従業員として会社に残ってもらう事で、許可の条件はクリアする事が可能になります。
対処法③財産要件や社会保険要件はすぐに対応する
500万円以上の財産要件や社会保険加入要件は満たしていなくても、すぐに対応すれば条件をクリアすることは可能です。財産要件の場合は、500万円を融資でもよいので借りてきて、許可取得後にその500万円を丸々返済しても許可を取り消される事はありません(いわゆる見せ金でもOKです)。これはこの財産要件が資金力ではなく資金調達能力を見る条件だからです。また社会保険については加入の届け出をすれば条件を満たせるので、加入していなければすぐに加入の手続きを行えばOKです。
建設業許可の取得後に条件を満たさなくなると?
建設業許可を取得後にこれらの条件が欠けた場合、許可は取り消されてしまいます。
※ただし④財産的基礎等だけは欠けてもOK
特に、経営業務の管理能力や専任技術者を1人の者に依存している場合は注意が必要です。その者が会社を辞めたり不慮の事故で働けなくなった場合、その時点で許可が取消になってしまいます。その人物が欠けてから急いで別の者を雇ってもダメです(欠けていた期間が生じた時点で許可が取消になる為)。そうならない為には、常に条件を満たした人物を複数人社内で抱えている必要があります。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
二 第八条第一号又は第七号から第十三号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
建設業許可の申請の流れ
ここまで紹介した条件を全て満たしていた場合、あとは建設業許可の申請を行えば許可業者になることができます。許可の申請は以下のような流れで行います。
①申請書類の作成
まずは許可申請書の作成を行います。この申請書類は以下のような様式のものが全部で20様式以上あり、初めて申請する方には非常に大変な作業になります。自治体によっては申請書の書き方の手引きが用意されているケースもありますので、申請先の自治体のホームページを一度チェックしてみましょう。なお、申請書類を全て見てみたいという方は「建設業許可の申請書類を全種類徹底解説!」の記事を参照ください。
申請書類の見本

②必要書類の収集
建設業許可の申請には申請者が作成する申請書と一緒に提出が必要な書類があります。例えば市役所で発行してもらえる「身分証明書」などの戸籍関係の書類や、法務局で発行してもらえる「登記されていないことの証明書」、また税務署で発行してもらえる「納税証明書」などがあります。また経営能力や専任技術者などの条件を満たしていることを証明するために、確定申告書の控えや会社の登記簿、銀行の残高証明など数多くの書類を収集しなければいけません。
申請書類の作成と合わせてこちらの書類収集も非常に大変な作業になります。これらの作業は申請者によって非常に大きな負担となるため、建設業許可の申請を専門とする行政書士に依頼する業者さんが非常に多いです。行政書士の選び方について詳しく知りたい方は「失敗しないための行政書士の選び方!」を参照ください。
③申請窓口で申請
申請書類が完成し一緒に提出する必要書類も用意ができれば、次は申請先の窓口にそれらの書類を持っていき申請を行います。申請窓口は都道府県の県庁の窓口や土木事務所、また各エリアの地方整備局になります。多くの自治体は持ち込みでの提出を義務としており、提出時に対面での書類審査があり不備などがあれば受理されずに補正を求められるケースが多いです。
ここまで紹介した建設業許可の申請の流れですが、より詳しく内容を知りたい方は「最短ルートで許可申請!建設業許可の申請の流れを徹底解説!」を参照ください。
建設業許可の種類と区分は理解しておこう
建設業許可の申請にあたっては許可の種類と区分を理解しておく必要があります。中でも「許可業種」と「知事許可と大臣許可の違い」、「一般建設業と特定建設業の違い」については必ず理解しておく必要があります。
建設業許可の業種
建設業許可は29種類の業種にわかれており、請け負いたい工事の種類によって取るべき業種を選択して許可を取る事になります(1つの業者が複数の業種を取る事も可能です)。業種は以下の通り2種類の一式工事(土木工事業・建築工事業)と、27種類の専門工事があります。自社がどの業種の許可を取る必要があるかは非常に重要なポイントになります。業種判断も専門知識が求められるため、少しでも悩んだ場合は申請先の自治体や専門の行政書士に相談されることをオススメします。この業種について詳しく知りたい方は「業種判断を間違うと大変!?建設業許可の29業種について徹底解説!」を参照ください。
| 略号 | 業種 | 略号 | 業種 |
| 土 | 土木工事業 | ガ | ガラス工事業 |
| 建 | 建築工事業 | 塗 | 塗装工事業 |
| 大 | 大工工事業 | 防 | 防水工事業 |
| 左 | 左官工事業 | 内 | 内装仕上工事業 |
| と | とび・土工工事業 | 機 | 機械器具設置工事業 |
| 石 | 石工事業 | 熱 | 熱絶縁工事業 |
| 屋 | 屋根工事業 | 通 | 電気通信工事業 |
| 電 | 電気工事業 | 園 | 造園工事業 |
| 管 | 管工事業 | 井 | さく井工事業 |
| タ | タイル・れんが・ブロック工事業 | 具 | 建具工事業 |
| 鋼 | 鋼構造物工事業 | 水 | 水道施設工事業 |
| 鉄 | 鉄筋工事業 | 消 | 消防施設工事業 |
| 舗 | 舗装工事業 | 清 | 清掃施設工事業 |
| 浚 | しゅんせつ工事業 | 解 | 解体工事業 |
| 板 | 板金工事業 |
知事許可と大臣許可の違い
建設業許可は、申請業者の「営業所」が1つの都道府県内にしか無い場合は知事許可を、営業所が2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合は大臣許可を申請します。知事許可と大臣許可で許可を取る為の条件や、許可の申請書類などは基本的には同じですが、申請先の窓口がそれぞれ都道府県か国(各エリアの地方整備局)かの違いがあります。また大臣許可のほうが申請手数料が高いといった違いもあります。知事許可と大臣許可の違いについて詳しく知りたい方は「うちはどっち?大臣許可と知事許可の違いをわかりやすく解説!」を参照ください。
なお、世の中の建設業許可を持っている業者のうち、90%以上が知事許可の保有者になりますので、この記事をご覧の多くの建設業者様も知事許可を申請するケースが多いと思われます。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可はある特定の条件に該当する工事を請け負う場合「特定建設業許可」という許可が必要になります。その特定の条件とは「元請業者として請け負った1件の工事において4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請け工事をだす場合」です(複数の下請業者と契約する場合は合計金額が上記金額を超える場合)。
上記以外の全ての工事については一般建設業許可で請け負うことが可能ですので、下請けしかやらないという業者は一般建設業許可で問題ありません。なお、許可業者の90%以上は「一般建設業許可」の保有業者で、「特定建設業許可」を取るためには通常より厳しい許可条件が課されることになります。詳しく知りたい方は「どれくらい難しい?特定建設業許可について徹底解説!」を参照ください。
建設業許可の取得にかかる費用
建設業許可を取るには、必ず以下の申請手数料がかかります。
| 申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
| 新規 | 9万円 | 15万円 |
| 許可換え新規 | 9万円 | 15万円 |
| 般・特新規 | 9万円 | 15万円 |
| 業種追加 | 5万円 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 | 5万円 |
手数料は申請時に現金で支払うか、もしくは9万円分の収入印紙を購入し申請用紙に貼り付けて支払います(支払い方法は各都道府県によって異なります)。この申請手数料は例えば許可の申請を取り下げたり、虚偽申請などを理由に許可が下りなかった場合には返金されませんので注意しましょう。
建設業許可の有効期限は5年
建設業許可の有効期限は、許可を受けた日から5年間で、その後は5年に一度の更新制となります。正確には、許可を受けた日から5年後の許可日の前日をもって満了となります。例えば、2020年4月1日に許可を取得した場合は2025年3月31日に許可が失効します。
許可は一度失効すると更新が出来なくなりますので、有効期限の管理は厳密に行う必要があります。許可の有効期限について詳しく知りたい方は「知らなきゃヤバイ!建設業許可の有効期限についてわかりやすく解説!」を参照ください。
許可申請でお悩みの方は
建設業許可の申請でお悩みの方は、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を代行してもらう方法があります。行政書士に依頼することで下記のようなメリットもあります。
行政書士に代行してもらうメリット
・申請を丸投げできるので業務に専念できる
・建設業法や許認可についての相談窓口ができる
・許可取得にかかる期間が短縮できる
当サイトを運営する建設業許可申請に専門特化した「イロドリ行政書士事務所」も申請代行サービスに対応しておりますので、許可申請を依頼したいという方はぜひ一度以下からご相談頂ければと思います(相談は無料です)。
まとめ
以上、ここまで建設業許可を取る為の条件についてご紹介してきました。
許可を取る為には絶対に抑えておかないといけないポイントですので、まずはこの条件を正しく理解して、自社の状況と照らし合わせていく事から始めましょう。許可条件の確認は建設業許可を取るための最初のステップとして非常に大切ですので、わからない事や不明な点があれば、申請先の自治体や専門の行政書士に相談されることをオススメします。