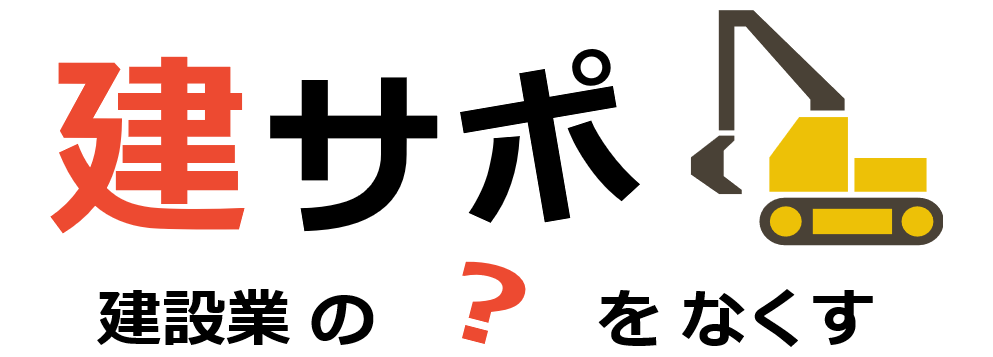既に建設業許可を持っていて業種を追加したいという場合「業種追加」という申請を行う必要があります。本記事では業種追加の概要や申請方法、また業種追加と間違いやすい申請区分などを詳しくかつ分かりやすくご紹介していきます。
本記事のポイント
持っていない業種を追加する場合に該当
手数料が5万円と他の申請区分より安い
般・特新規と間違いやすいので注意
業種追加ってどんな申請なの?
建設業許可を申請する際、その申請の目的や申請業者の許可保有状況などに応じて、該当する「申請区分」というものを選択しなければなりません。業種追加はその申請区分のひとつで、現在保有する許可区分と同じ区分で保有していない業種を申請する際に該当する申請区分です。定義だと少しわかりにくいですが、名称の通り業種を追加する際はまずこの申請区分を想定すれば良いです。ただし、見た目は業種追加でも申請区分上は業種追加に該当しないケースもあるので注意が必要です(後程詳しく解説します)。
ちなみに他にも申請区分は以下の5つがあります。詳しく知りたい方は「許可の申請区分5つをわかりやすく徹底解説!」を参照ください。
| 申請区分 | 該当要件 |
| 新規 | 現在許可を受けていない者が許可を申請する場合 例)許可なし⇒管工事業 |
| 許可換え新規 詳しい解説を見る | 現在許可を受けている行政庁以外の行政庁に対し新たに許可を申請する場合 例)管工事業(知事許可)⇒管工事業(大臣許可) |
| 般・特新規 詳しい解説を見る | 一般建設業許可のみを受けている者が新たに特定建設業許可を申請する場合、又はその逆 例)管工事業(一般)⇒管工事業(特定) |
| 業種追加 | 現在保有する許可区分(一般・特定)と同じ許可区分で保有していない業種を追加申請する場合 例)管工事業(一般)⇒管工事業(一般)+塗装工事業(一般) |
| 更新 詳しい解説を見る | 既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請(更新)する場合 例)管工事業(一般)⇒管工事業(一般) |
業種追加に該当する具体歴なケース
業種追加は先ほど述べた通り、すでに持っている許可区分(一般・特定)と同じ区分許可で、現在持っていない業種を追加したい場合に該当します。例をあげると下記のようなケースがあげられます。
管工事業(一般)の保有業者が塗装工事業(一般)を申請
電気工事業(特定)の保有業者が管工事(特定)を申請
管工事業(特定)と塗装工事業(一般)の保有業者が屋根工事業(一般)を申請
業種追加の抑えておかないといけないポイントは持っている許可区分と同じ区分で業種を追加する場合に該当するということです。許可区分とはここでは一般建設業か特定建設業かということを指しています。つまり一般を持っている業者が特定の許可業種を追加する場合は、見た目上業種を追加しているのですが申請区分上は業種追加に該当しません。ここが非常に間違いやすい点ですので詳しく見ていきましょう。
業種追加と般・特新規は間違いやすいので注意
業種追加で気をつけないといけないのが、般・特新規との判定間違いです。先ほどご紹介した一般建設業の許可業者が特定建設業の業種を追加するケースは、業種追加ではなく「般・特新規」という申請区分になります。
この般・特新規は、持っている許可区分(一般・特定)とは異なる許可区分の許可を申請する場合に該当する申請区分になります。その為、見た目は業種を追加していても、その業種が持っていない許可区分であれば般・特新規という扱いになります。それでは具体的な事例を見ながらどちらに該当するか考えてみましょう。
管工事業(一般)と塗装工事業(一般)を持っている業者が、屋根工事業(特定)を追加する場合
⇒般・特新規になります(持っている許可区分と異なる区分の業種を追加するため)。
管工事業(特定)と塗装工事業(一般)を持っている業者が、屋根工事業(特定)を追加する場合
⇒業種追加になります(持っている許可区分と同じ区分の業種を追加するため)。この場合は、もともと一般も特定もどちらも持っているので、一般を追加しても特定を追加してもどちらも業種追加に該当します。
管工事業(一般)と塗装工事業(一般)を持っている業者が、屋根工事業(特定)と大工工事(一般)を追加する場合
⇒般・特新規と業種追加をどちらも同時に申請することになります。この場合は、建築工事業については般・特新規、大工工事業については業種追加でそれぞれ申請します。
業種追加の申請実務上の特徴
業種追加は他の申請区分と比較し、必要な申請書類がやや少なくなり(一部省略可能な書類がある)、また最大の特徴は申請にかかる手数料が安い点です。業種追加は知事許可であっても大臣許可であってもどちらも5万円と、他の申請区分がどれも9万円(大臣は15万円)であることを考えるとリーズナブルです。また同時に申請する場合は何業種追加しても手数料は5万円で変わりません。ただし、特定と一般の両方を同時に追加する場合は、それぞれに5万円がかかりますので合計10万円の手数料が必要です。
また業種追加は許可業者に付与されている許可番号も変わりませんのでその点も安心です。
【注意】許可の有効期間について
業種追加で許可業種を追加した場合、許可の有効期間は取得してから5年間ですので、当然すでに持っている許可業種と新たに追加した許可業種ではその有効期期間が異なることになります。そうなると、許可の期限管理が煩雑となり、また更新手数料も個別にかかってしまうのでデメリットが大きいですね。
もちろんそれぞれの期限を把握しきちんと管理できればそれで問題ないですが、それらが面倒だという場合は、後から追加した許可の有効期間と既存の有効期間を1本化できる制度が用意されています。この制度を利用すれば、どちらかの有効期間にそろえることが可能になり、許可管理や手数料の一本化も可能です。以下で詳しく解説していますので興味のある方は参考にしてみてください。
許可申請でお悩みの方は
建設業許可の申請でお悩みの方は、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を代行してもらう方法があります。行政書士に依頼することで下記のようなメリットもあります。
行政書士に代行してもらうメリット
・申請を丸投げできるので業務に専念できる
・建設業法や許認可についての相談窓口ができる
・許可取得にかかる期間が短縮できる
当サイトを運営する建設業許可申請に専門特化した「イロドリ行政書士事務所」も申請代行サービスに対応しておりますので、許可申請を依頼したいという方はぜひ一度以下からご相談頂ければと思います(相談は無料です)。
業種追加についてまとめ
以上、ここまで業種追加についてご紹介してきました。
事業を拡大していく中で元請からの要請や社員の採用で許可要件を満たした等様々な理由で許可業種を追加するケースは出てきます。般・特新規との判定や有効期間の複雑化等、色々と考慮すべき点も多いため、本記事を参考にしっかりと概要を理解されたうえで申請を進めていくようにしましょう。