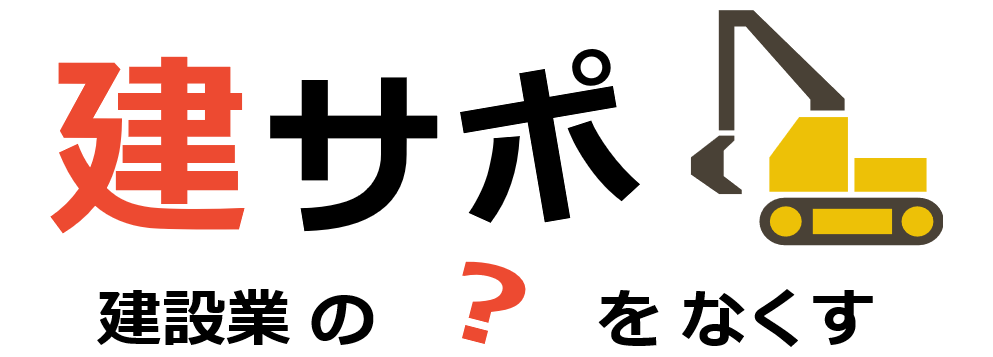建設業許可の申請をする際「登記されていないことの証明書」という書類が必ず求められます。普段の生活であまり耳にする事は少ないと思いますがどういった書類でどこに行けば手に入るのでしょうか?本記事では「登記されていないことの証明書」について詳しく解説していきます。
本記事のポイント
本証明書=成年後見人制度の利用有無証明
許可の欠格要件非該当の判断の為に必要
法務局(本局)で取得可能(郵送も可)
登記されていないことの証明書とは
登記されていないことの証明書とは,成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記されていないことを証明する公的証明書です。つまりどういう事かと言うと、証明者が成年後見制度を利用していないことを確認できる書類ということです。書類の見本などは後ほど詳しくご紹介するとして、まず簡単に成年後見制度について簡単に説明しておきます。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、例えば認知症や知的障害など意思決定や判断能力が十分でない者をサポートするために、その者にサポート者をつけて、そのサポート者に財産の処分や売買契約などの権利を与える制度です。そのサポート者は、与えられる権限の大きさによって成年後見人、保佐人、補助人、サポートされる者を成年被後見人、被保佐人、被補助人に分けられます。
成年後見人にはかなり強力な権利が与えられるので、国がきちんとした管理を行う必要があり、その為この成年後見制度の利用者は必ずそのことを登記しなければいけません。つまり言い換えると、この成年後見制度に関する登記有無は下記のような状態を表します。
登記されていない=成年後見制度利用者でない
欠格要件に該当しない事を証明する為に必要
そではなぜ、成年後見登記がされていない事を証明する書類が許可申請時に必要なのでしょうか?その理由は、建設業許可の要件のひとつ「欠格要件に該当しないこと」を証明するためです。
欠格要件とは、その要件に該当すると許可を受ける事ができない事項で、例えば暴力団関係者であるとか、過去に犯罪歴があり刑務所を出所してから5年たっていないとかいくつかの要件があります。その欠格要件のひとつにより、建設業許可を申請する本人や会社役員は、「成年被後見人」および「被保佐人」でない事が許可の条件とされています。そのため、許可申請時にその事実を確認する為に「登記されていないことの証明書」が必要なのです。
登記されていないことの証明書を見てみよう
では実際に実物見本を見てみましょう。登記されていないことの証明書は以下のような書類になります。

あれ?手書きなの?と思われた方もいると思います。この登記されていないことの証明書を発行するためには申請書を作成し提出しなければなりません(後ほど説明します)。この申請書にかかれている内容が一部そのまま利用されるため、申請書を手書きで書けば、それがそのまま反映されるのでこちらの見本のように手書き部分でてきます。
登記されていないことの証明書の入手方法
登記されていないことの証明書の入手方法は窓口申請と郵送申請の2つです。尚、許可申請時に提出する本書類は申請日前3カ月以内に発行されたものである必要がありますので注意しましょう。
窓口申請の方法
全国の法務局や地方法務局の本局の戸籍課で申請から受け取りまでが可能です。支局や出張所ではダメで、本局でないと申請出来ませんので注意しましょう。
申請書も窓口でもらえますが、事前に法務局のHPでダウンロードできますので、事前に記載して持参するとスムーズです。窓口がすいていれば数分で受け取ることが可能です。なお、住所地や本籍地による申請窓口の制約はありませんので、全国どこの法務局でも本局であれば受け取ることができます。
郵送申請の方法
郵送でも申請から受け取りまで可能です。その場合の窓口(申請書送付先)は、住所地や本籍地に関係なく全て東京法務局後見登録課になります。窓口受取と違うのは少し時間がかかる点です。申請書を送付してから手元に届くまでに約1週間から10日程度を見ておきましょう。窓口に足を運ぶ必要はありませんが時間がかかるのでご自身の状況に合わせて入手方法を選びましょう。
登記されていないことの証明書入手までの流れ
では「登記されていないことの証明書」を入手するために一連の流れをご紹介します。
① 申請書作成
指定の書式の申請書がありますので、必要事項を記載し提出します。証明を受ける方に関する記載内容の一部(氏名や住所・本籍など)がそのまま証明書に反映されますので、間違いがないように記載しましょう。
申請書は下記ページで入手可能です。
「東京法務局HP」
② 添付書類(本人の確認書類)
証明書の対象者本人が申請する場合、本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)の提示が必要です。郵送で申請する場合は上記書類のコピーを同封します(どれかひとつで可)。なお、申請を親族やそれ以外の代理人が行う場合は、親族であることを確認できる書類(戸籍謄本)や委任状も別途必要になってきます。
③ 申請手数料
申請手数料が1通につき300円かかります。現金で支払うのではなく、申請用紙の所定の箇所に必要額の収入印紙を貼ります。収入印紙は郵便局や法務局の印紙売場で購入可能ですので、窓口申請の場合は申請先の法務局で、郵送申請の場合は郵送する郵便局で直前に購入すればOKです。
④ 返信用封筒(郵送申請の場合)
郵送での申請と受取を希望する場合は、返信用封筒(必ず切手を貼る)を申請書に同封しましょう。発行枚数が1,2通であれば長3号封筒(定形内)84円切手でOKです。
【ポイント】申請時の注意点
この登記されていないことの証明書は、申請時に以下の3つからどの範囲の情報が必要か選択して申請します。
①成年被後見人、被保佐人とする記録がないこと
②成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がないこと
③成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がないこと
建設業許可の要件で求められるのは「成年被後見人」および「被保佐人」でない事なので、①の範囲の証明を申請すればOKです。申請窓口で迷いがちですのでここは押さえておくようにしましょう。
身分証明書との違い
建設業許可の申請時に必要な書類で登記されていないことの証明書と似たような書類があります。それが「身分証明書」です。この身分証明書も、登記されていないことの証明書と同じく欠格要件に該当しない事を証明する為に必要な書類です。そのため非常に混同しやすいのですが、これらは以下のようにその記載内容と発行元がそれぞれ異なります。
禁治産又は準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明する書類で、戸籍を管理する役所が発行する証明書
後見登記ファイル上に後見の登記がされていないことを証明する書類で、登記を管理している法務局が発行する証明書
この2つの書類は必ずどちらも必要です。詳しい話をすると、後見制度開始前に、現在の成年被後見人や被保佐人に該当する人物だった場合、身分証明書の禁治産や準禁治産の記載を確認しないとわからないため、両方の書類で確認を行うことになっています。
申請書類作成でお困りの方は
申請書類の作成でお困りの方は、当サイトを運営するイロドリ行政書士事務所にお気軽にご相談下さい。建設業許可申請を専門とする行政書士が対応させて頂きます。
また建設業に特化した当事務所では申請代行サービスも対応しておりますので、許可申請を丸投げしたいという方はそちらをご利用頂ければ、楽に許可取得が可能です。
登記されていないことの証明書まとめ
以上、ここまで登記されていないことの証明書についてご紹介しました。
日常生活の中でこの書類が必要なシーンはほとんど無いと思いますので聞きなれない書類だと思いますが、取得が難しいものではありません。ただし必ず法務局の「本局」にいくということだけは忘れないようにしましょう。